放哉のひとり
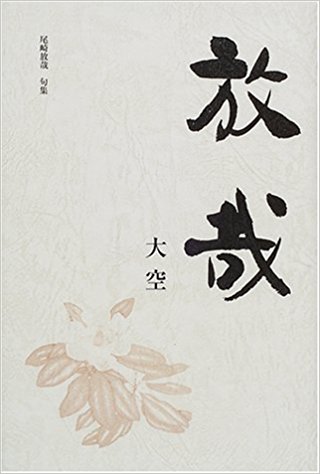
咳をしてもひとり
俳句のことはよく知りませんが、尾崎放哉のこの句は知っていました。
尾崎放哉 1885年(明治18年)1月20日 - 1926年(大正15年)4月7日)
東京帝国大学法学部を卒業、東洋生命(現朝日生命)保険に就職し出世コースを進んだエリートだったが、職も妻も捨て、寺を転々としながら俳句を詠む。
最後は小豆島の庵寺で極貧の中病に伏し、島の漁師夫妻の手に抱かれて41才で亡くなる。
酒による失敗やクセのある性格から周囲とのトラブルも多かった。
(wikipediaと句集「放哉」から抜粋)
酒におぼれ、妻や親戚から見放され、友人だけでなく終の棲家と決めた島の住人にまで無心しながら、一方で学歴を鼻にかけていたと聞くと、私なら決して関わりをもちたくないタイプの人です。
でも、この句は衝撃でした。
何もない、のです。
まわりに誰も、何もない。ただ、ひとりなのです。
そのひとりも、寂しいとか哀しいとか嬉しいとか、高揚するものや打ちひしがれるものもありません。
こんなにそぎ落として、詠む句。
それなのにこの圧倒される感覚は何だろうか、とずっと思っていました。
句集「放哉 大空」を刊行した、彼の恩人でもある萩原井泉水の序の言葉を読み、ああ、そういうことなのかと腑に落ちました。
ちょっと長いですが引用します。
その人の風格、その人の境地から生まれる芸術としての俳句は随一なものだと思ふ。
俳句は「あたま」だけでは出来ない、「才」だけでは出来ない、「上手さ」があるだけ、「巧みさ」があるだけの句は一時の喝采は博し得ようとも、やがて厭かれてしまふ。
作者の全人全心がにじみ出ているやうな句、もしくは作者の「わたくし」がすっかり消えているような句(この両極は一つである)にして、初めて俳句としての力が出る、小さい形に籠められた大きな味が出るのである。
(中略)
而して、そのような本当の俳句を故尾崎放哉君に見出したのである。
「作者の全人全心がにじみ出ることと、作者の「わたくし」がすっかり消えていることは一つである」
これだったのです!
「わたくし」がすっかりなくなった時に初めて現れる、全人全心の「己」。
二人や三人、の世界での一人ではない、「ひとり」
私やあなた、の世界ではない、「ひとり」
そんな「ひとり」になったことはありませんが、なぜか惹かれるもの、憧れさえ感じます。
萩原井泉水が言う、何も持たなくなった時に、全てが与えられるような世界。
入れ物はない 両手でうける
蓄えておく入れ物を持たない者こそがうける、はかり知れない恵みを感じます。
かといって放哉は聖人ではなく、どうしようもない自分を知っていました。
その自分を抱え続けたからこそ、「わたくし」をすっかり消す瞬間をとらえられたように思います。
私の好きな句をもう一つ。
追っかけて 追いついた風の中

YouTubeで放哉の句があったので、よかったらご覧ください。